タップで読む
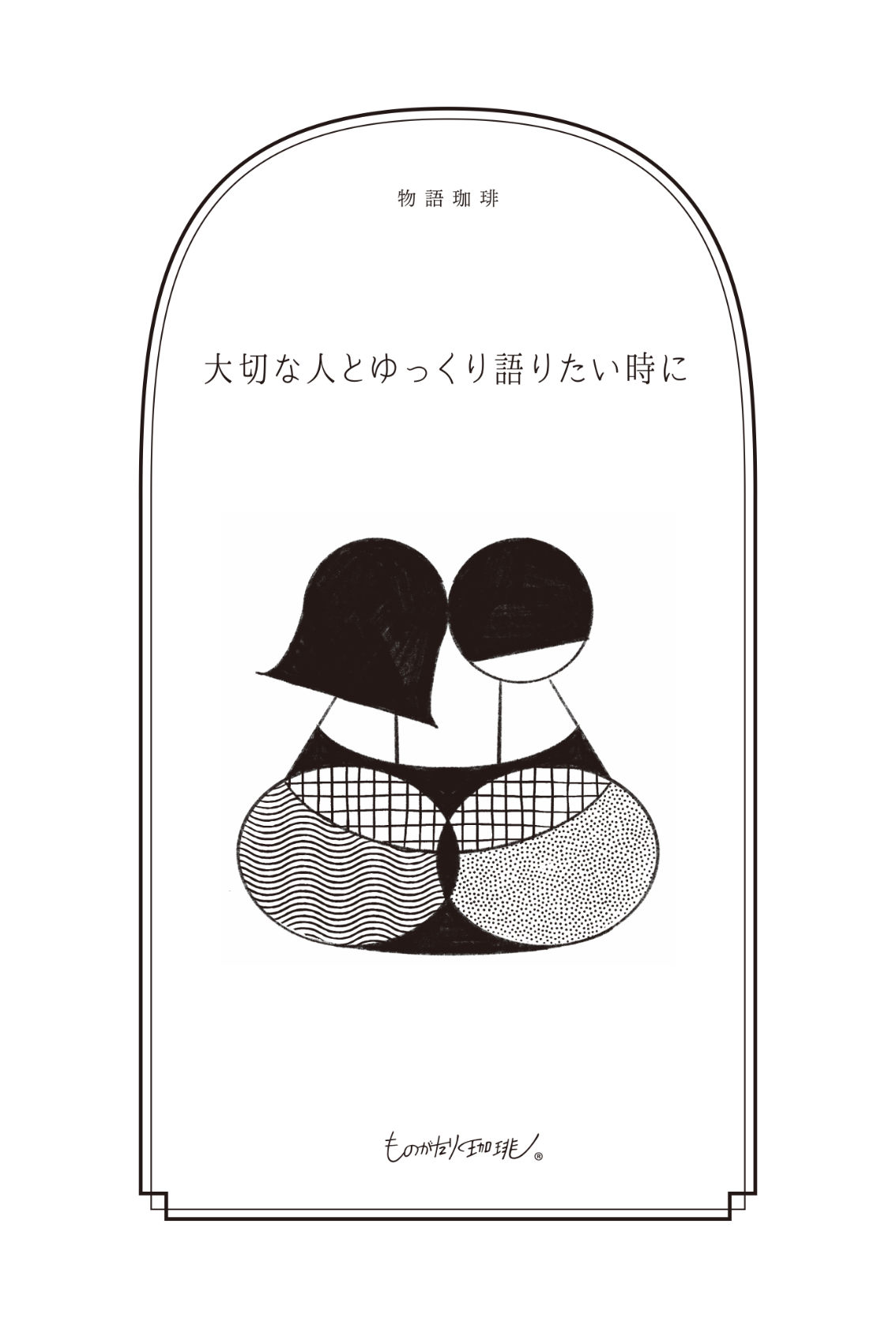
大切な人とゆっくり語りたい時に
手術を受けたのは、夏の初めだった。覚悟していた喪失感よりも、現実の痛みの方が鮮明で、私は朝に目が醒めて、微睡みの中で昼をやり過ごし、夜また眠り、そして翌朝目醒めることだけを、ただそれだけを繰り返すことでいっぱいだった。その一見単調に見える反復だけが、希望であった。ひと月ののち、私は念願であった村の自宅に帰ることはできたものの、その実は単に天井の景色が変わったに過ぎなかった。それでも、この土地の、短くも眩しい夏が過ぎ、柔らかな色彩の秋が訪れ、寒気でその色が一段ずつ深くなってゆくころになってやっと、少しずつ生が実感を帯びてきた。
「おはよう、マイ。今日の気分はどう?」
毎朝、夫は私に尋ねる。私は、吐き気がするとか腕が痛いとか浮腫がひどいとか、ありとあらゆるバリエーションの不調を訴える、確かに私の身体は毎日どこかが痛むのだ。彼は、そんな私の気の滅入る朝の挨拶にも、いちいち仔細にわたって具体的な症状を尋ね、時刻とともに記録する。彼が現実的にその詳細な記録を読み返したり、具体的に活用しているのかは関知していないけれど、確かにそれで私は満足する。私が毎日を生き延びている記録だから。
私が身繕いをしている間に、彼はキッチンの小さなテーブルでコーヒーを作る。私はその光景を見ているのが好きだ。黙ってキッチンの入口に立ち、暫し眺める。陽の降り注ぐ、大きな窓辺に向かって立つ細長い彼の背中が、眩しいひかりに影絵みたいに浮かんでいる。その幸福な景色に、私は暫く息を呑む。ロンドンの小さなフラットを売って、この田舎のこぢんまりしたファームハウスを譲り受けたのは私たちにとって幸運だった。ベッドの中で窓から眺めるだけの私は殊更に、自然に囲まれて生きるしあわせを感受していた。こんな晴れた朝はもちろん、仄暗い雨の日に感じる、湿度の甘い匂いや、鈍色の空に、雲が幾千もちぎれ飛ばされてゆく姿を、私は心からうつくしいと思い、飽かず眺める。
おはよう、と私はもう一度言って、彼に向き合って卓につく。朝の儀式と彼が呼ぶその所作は、やはり神事やまじないのようだ。銀のポットに、華奢なガラスのドリッパーをのせ、フィルタをそっとセットする。湯通しのために熱い湯を注ぐと、ふわりと湯気が立つ。慎重な面持ちで、コーヒー豆の重さを正確に量り、グラインダーへ。ポットに残る湯を捨て、ドリッパーに挽いたコーヒー豆をそっと匙で掬って入れ、真ん中に小さなくぼみを作る。これが目印なんだよ、と言って、私ににっこりとして見せる。湯が注がれると、あたりにぱあっと華やかな香気が舞う。私は深呼吸する。満足そうに夫は彼の儀式を続ける。そんなふうに、私の生活は、多少の痛みを伴いつつも、ごく平穏に続いていた。
ある日、夢が、私をあの場所へ連れてゆくまでは。
夏の宵だった。私が歩く街路の先を、点々と橙色の街灯が照らしている。大気に甘い湿度が満ちていた。ああ、ここは、私の母国だ、直ぐに思った。街並みは、無機質なビルの合間に、極彩色の看板がひしめく雑多な風情で、街路に沿って建ち並ぶ店舗の内部はおしなべて平坦で、眩しく白いひかりに充ちている。私は気まぐれに、ひとつのコンビニエンス・ストアの自動ドアを踏んだ。一歩進むと、忽ちに降り注ぐ音とひかりの洪水に、一瞬目が眩む。そして鼻腔にむっと押し寄せるのは、揚げ物や、様々な食べものの匂い、コーヒーマシンから溢れる香気。その混沌を私は、胸いっぱいに吸い込んだ、その時。
ふと見ると、目の前に、父がいた。
見間違うわけはない。アイスクリームのケースの前で、商品を手に取ってかごに移しているその丁寧な仕草が、まさにそのひとであった。見慣れたネクタイ、妹と私が選んだ柄の、そして左手に下げている、いつもの鞄。かごには、苺のアイスクリームを三つ。母と私たち姉妹の好物で、父はよく会社帰りのおみやげに買ってきてくれていた。あの頃、彼が私たちを置いて去る以前の。
私は凝視する。父はけれども、私の覚えているそのひととは少し違っている。髪は白いものが混じり、その手はごつごつとしていて、痩せて皺の目立つ目もと。二十年の年月を私は思った。「お父さん。」声は、出なかった。私は父が会計をして、その袋を大事そうに下げて、店を出てゆくのをただ見ていた。
目が醒めてしばらく、私は起き上がれなかった。夢の中とは言え、久しぶりに触れた故国の気配に、圧倒されていた。あの混沌、甘い湿度と、夏の夜の熱気。むせ返るような、泣き出したくなるような郷愁と、微かに胸を刺す苦みは、父の姿のせいだろう。精神の動揺に呼応するかのように、次第に身体に重い痛みが走り、私は起き上がれないまま、ぼんやりと布団にうずくまっていた。
夫が私の様子を見に来たのは、十時を回ってからだった。大丈夫?ひどい顔しているよ。彼は小さい声で尋ねた。コーヒーを作ってくれる?私は身体を起こして、室内履きに足を入れながら言う。そのラベンダー色の絹の小さな履きものは、私の小さな足にとても似合った。去年の夫からのクリスマスの贈りもの、彼の好むもの。日本の夢を見たことは、なぜだか彼に話す気にならなかった。今朝はミルクを温めて、大きなマグにコーヒーと半々に注ぐ。その甘い香りの飲み物を受け取って、甘やかされた気持ちでそっと唇をつける。窓の外で、鴉がぎゃあと啼いた。未明から、乾いた風がびゅうびゅうと吹きすさんでいる。冬が、始まるのだ。
痛みや熱で身体の自由が奪われると、想像力が思いもかけないほど豊かに、鮮やかに、跳躍することがある。そのことを私は知った。動かない四肢の代わりに、起き上がれない頭を抱えて、私の精神はどこまでも自由に飛び回ることができる。私に見えるその世界は、鮮やかな極彩色が彩る天国と地獄だ。天上の庭園と、燃え盛る煉獄の幻影は、私には等しくうつくしい。私には、その浮遊を楽しんでいるふしがあった。恍惚として、見惚れていたい。それがたとえ、わが身を焼く業火であっても。この不自由な身体が息絶えるせめてその時まで。私は願う。どうかこの世界のうつくしさを見ていられますように。
ある夜、私は夢で妹と邂逅した。
待ち合わせの混み合ったホテルのラウンジで、妹は赤ん坊を抱いてソファに腰掛けていた。彼女が背にしている一面の大きな窓からは、冬の午後の優しいひかりが射していて、ふわふわとした子どもの髪の毛を、金色に輝かせている。妹は目を細めて、腕の中の赤ん坊を見ている。母の死後に私たちが喪失し、そしてまた彼女が自身の手で取り戻したのであろう、その黄金色の平穏を、私は眺めていた。
私たち家族は、正確には残された私と妹のふたりだが、母が亡くなったのを機に、円満に解消することにした。父は他に家庭を持っていたし、母はもういない。母の死後、私たちは家や家財道具の一切合財を処分して、手元に残った現金をぴったり等分に分けた。少女時代の幸福な思い出を巻き込んだまま、私たちはあの深く抉られた癒えることのない傷に、重く厚い蓋をした。もう二度と思い出さないことでしか、私たちは、この先もまだ自分たちの人生は続くことに折り合いをつけられなかった。
久しぶりに会った妹は、饒舌に語った。仕事のこと、結婚したこと、暮らしている街のこと、その言葉には、希望が満ちていて、彼女のまわりには、明るいひかりの鱗粉が舞っていた。私は、ただただにこにこと頷いて、その話を聞いていた。幸福の金色が、私の方にもひたひたと押し寄せて、私はその甘美な空気を肺いっぱいに吸い込む。だから目が醒めて、それが夢だと気がついたときの私の落胆は、とても深かった。妹は、赤ん坊を抱いて、あの明るい世界で、ほんとうに生きていてくれるのだろうか。泣いているの?隣で眠っていたはずの夫が、私の頭にそっと掌をのせて訊く。妹の笑顔が、まだ記憶の端々に残っていて、私はその突然の喪失に動揺している。
「マイ、話してくれないか。きみは最近ずいぶんと鬱ぎ込んでいる。目醒めている時間も、ほとんどひとりで寝室に籠もることが多いね。病気のことで、なにか思い悩んでいるのかい。なにか私が力になれることはあるかな。」
私は答えずに、目を閉じた。
英国人の夫と出会ったのは、日本を離れてもうずいぶんと経った時分であったので、私は自分のことを天涯孤独の身と紹介した。彼は静かに、私の孤独を受け入れた。彼が私に与えてくれたものは、ふたりだけの孤独だった。私たちは、友だちも、家族や親戚も、近所付き合いも、旅行も好まなかった。ロンドン郊外にごく小さなフラットを買い、必要なだけの仕事をこなし、あとはふたりでひっそりと時間を過ごした。映画、音楽、ワイン、おいしいものをちょっとだけ楽しむような食事、毎夜お互いの腕の中で眠り、朝には丁寧に淹れる温かなコーヒーを一緒に飲む、その繰り返し。その暮らしの中で、私は過去の郷愁を捨てた。故国の、あの雑多な混沌も甘い湿度も温かい家族の記憶も、全部忘れたものとして生きてきた。もうずっと、長いあいだ。
母が少しずつ蝕まれてゆくのを見るのは、とても辛かった。私も妹も、現実から少しずつ離反してゆく彼女の精神を、幸福であった家族の記憶で繋ぎ止めようとしたけれど、それは単に徒労であった。それは、まだ若い私たちが人生で初めて直面した、完全な拒絶と挫折だった。涸れるまで、幾度も叫んだ私の声は、ついぞどこにも届かなかった。
どうしたの、マイ?夫が私を揺さぶるので、はっと目が醒めたような気持ちになった。私はほんとうに、声を発していたのだろうか。今も、あのときも。「日本の、昔の夢を見ていたの。」そう言った私の声は、思ったよりもごく小さく響いた。
そして私は、長い話をした。
父が出ていったこと、妹と母と三人の暮らしで、その不在がぶくぶくと肥え太り、その圧を増していったこと、母が少しずつ蝕まれて、生活がおかしくなっていったこと、そしてある日突然に帰らぬひととなったこと、残った私たちが過去の一切を放棄したこと、そして生死の境で闘病する今、動かなくなった身体から飛び立つように、私の精神だけが何かと繋がろうとしていること。
私が、自分の昂る感情を彼の前に晒したのは、これが初めてだったと思う。私は、彼と過ごす穏やかな空気を好んでいた。日常を一緒に暮らす中で、波立つような小さな感情の揺れはあるものの、敢えてそれを明確には口にしなかった。そんな折の私は、ひとりでひっそりとその波が去るまで、言葉を飲み込んで自身の殻の中に沈んだ。彼は優しかった。ただ、絶対に踏み込んでは来ない。私たちは、それを私たちの望む平穏だと思っていた。
話している間、私の声は終始震えていた。私は自分が、何かを壊してしまったのではないかという不安に怯えた。夫はいつもの静かな声で、話してくれてありがとう、と私を抱きしめて言った。そっとガウンを着せて、促してキッチンへと向かう。夫はそのまま黙して、彼の朝の儀式を執り行った。空気に華やかで温かなコーヒーの香りが漂う。冬の初めの、遅い夜明けを迎えた頃だった。橙色の生まれたばかりのひかりが、窓辺を包んでいる。私にカップを手渡しながら、彼が口を開く。
「マイと暮らすようになって、言葉にするものとしないものの境について、僕はずっと考えていた。きみは、明確な言語で語り合うよりも、表情や声のトーンや気配で感じ合うことを好むね。その互いに溶け合うみたいな感覚は、僕にとっては新鮮だった。マイの微笑みや、苦しそうな息や、ため息や、鼻歌で、僕はきみの喜びや苦しみや痛みや嬉しさを感じようとしたし、理解したと思っていた。」
それは私も同じだった。私たちは幾百もの夜を共に過ごしながら、私たちは、互いに相手に投じる自身が捏造した幻影を見ていたのかもしれない。熱く甘いコーヒーを一口飲んで、私は彼に語りかける。これからは、私が私に見えているものを、その心の風景を、その揺らぎも、高揚も、私は言葉にしてあなたに届けよう。そしてあなたもまた、あなた自身の世界を、言語で描いて応えるだろう。一つ一つの言葉は不完全でも、それを重ねて対話を繰り返すことで、私たちはほんとうの互いの像を結ぶ、確かなぬくもりを伴って。そうして初めて、私の声は、あなたのこころに届くはずだから。
- 著者 岡田環
- 一九七四年、北海道生まれ。モスクワからの放送を聞こうと短波ラジオにかじりついていた十四歳は、もうずいぶんと長いこと旅をしています。暮らした国は、十一カ国め。物語を書くこと、写真を撮ること、料理をすること、それが今の私の表現です。現在はアゼルバイジャン、バクー在住。
- コーヒーについて
-
日々感じている素直な気持ち、思い出を懐かしく思う気持ち、これからの未来に馳せる想い。 そんなお互いの想いを大切な人とゆっくりとシェアできる時間は何にも変えがたい幸せな瞬間ではないでしょうか。 今回のコーヒーは、ホットチョコレートのようなほっこりする甘さの中に、オレンジの爽やかな果実感を加えた心地よいブレンドです。この一杯をきっかけに大切な人との関係がより深まる時間を紡げますように。